通勤中でも家事中でも、本の世界に浸れるのがオーディブルの魅力。
本屋で「ぶ厚い…」と尻込みする大作も耳ならすっと入れるし、定額だから普段読まないジャンルにも挑戦できる。
今回紹介するのは激烈に怖いことでバズりにバズった傑作『近畿地方のある場所について』です。

いわゆる「閲覧注意」な一作ね…。
聴くには覚悟が要るわよ。
あらすじ
制作:2023
著者:背筋
近畿地方の山間部に存在すると噂される“ある場所”をめぐる複数の証言。
そこに描かれるのは観光地のポスターに載るような牧歌的な風景ではなく、地図からも意図的に消されたような領域だ。
登場人物は偶然その場所に迷い込んだ青年や家族、学生グループ、そこで何かを見た老婆などなど。
それぞれが異なる経緯で“そこ”に関わり、奇妙な現象や不可解な人物と遭遇する。
物語は短編連作形式で進み、各エピソードは独立しながらも断片的な情報が積み重なっていく。
やがて読者はその土地にまつわる長い時間の層と、正体不明の力の存在を感じることになる。
極端に怖い、最先端のホラー小説
これにはやられた。マジで怖い。
ホラー映画好きの私だが、ホラー小説に関して言えばこれまでイマイチぴんと来なかったのが正直なところだ。 いにしえの『リング』や『ぼっけぇ、きょうてぇ』、比較的最近では『ぼぎわんが、来る』などのヒット作は追いかけてきた。 どれも怖くはあったが、やっぱり恐怖のパンチ力としてはホラー映画が勝るなーと思っていた。字じゃなぁ…みたいな。
浅はかだったと言わざるを得ない!
『近畿地方のある場所について』はもう、とことん怖い。
昨今流行りのモキュメンタリー(フィクションを本当っぽく描くフェイクドキュメンタリー)を取り入れた恐怖描写は、読者の想像力が恐怖を補完するというコンセプトの極致。
映像がないからこそ、脳内で勝手に増幅される“見えない何か”がこちらの生活圏にまで侵入してくる。
しかも証言者ごとに語り口が微妙に異なり、信憑性の揺らぎが恐怖を倍増させる。
ある話では淡々と「そこにいた」とだけ語られ、別の話では息を切らしながら「逃げた」と繰り返す。読者はその差異を埋めようとして、かえって深みにハマる。
この構造は、ドッキリ系ホラー映画のとは別種の持続的な不安を生み出す。 ページを閉じても、頭の中でまだ誰かが喋っている。
恐怖は耳から侵入する
オーディブル作品として本作を鑑賞した場合の短所について先に触れておこう。 挿絵が見づらい。これに尽きる。
例の鳥居のイラストや終盤の大口少年の挿絵などを見るには、「いったんスマホの画面に戻って所定のリンクをタップして見る」というプロセスを踏む必要がある。 紙の本ならページをめくれば自然と目に入ってくる挿絵を直感的に味わえない点は、オーディブルの大きな弱点だ。
だがそれを補って余りある利点がオーディブルにはある。 臨場感だ。
複数の登場人物が登場してそれぞれの恐怖体験を語るという短編集スタイルの本作だが、ナレーターの演技力の高さもあり各エピソードの個性が際立っている。声色や間の取り方ひとつで、同じ作品内でもまったく別の温度を帯びるのだ。
そしてオーディブルなら背筋氏の関連作、『穢れた聖地巡礼について』と『口に関するアンケート』も聴ける(※2025年9月現在)。お得。
どっぷり「最先端の恐怖」に浸かるこのチャンスを逃す手はない。 なお両作とも音声ならではの恐怖ギミックがちょっぴりだけ仕込まれている。
紙か音声かは好みだが、この作品の本質はどちらでも変わらない。 『近畿地方のある場所について』は、読者(あるいは聴者)の想像力を人質に取る。
ページを閉じても、イヤホンを外しても、ふとした瞬間にあの声が蘇る。
そういう意味で本作はホラー小説の新しい形態を、すでに一歩踏み出している。

オーディブルをまだ使ったこと無い人は、下のリンクから是非試してみて。
最初の一か月は無料だし「思ってたんと違うな~」だったら解約すればいいし。
↓当ブログのオーディブル関連記事まとめはこちら
↓いちいち全部怖い関連作。背筋氏、いったい何者…。



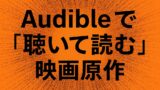



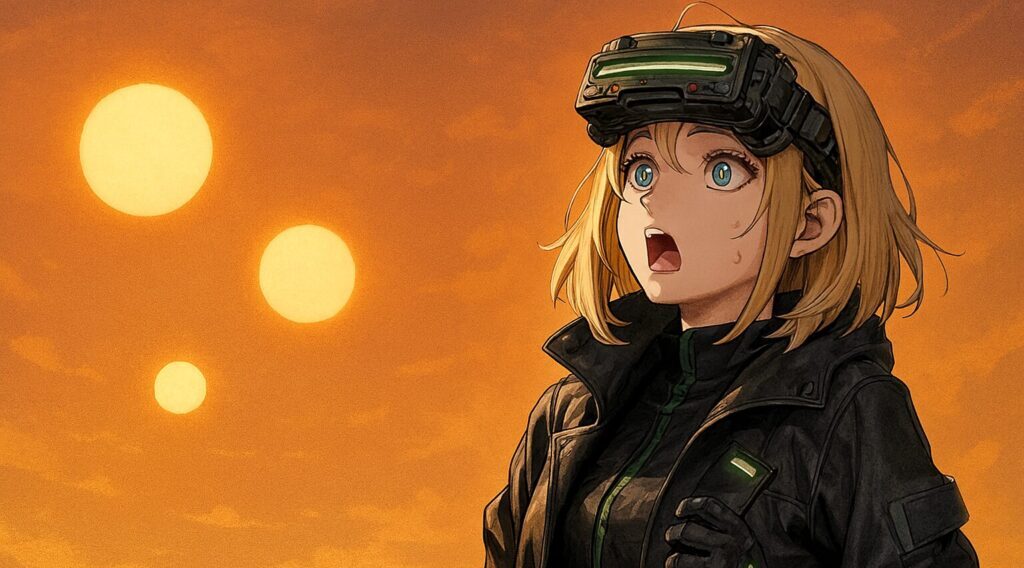
コメント