今回は『怪物はささやく』の紹介です。

『パンズラビリンス』みがある佳作。

2016年 スペイン・アメリカ
監督:フアン・アントニオ・バヨナ
出演:ルイス・マクドゥーガル、シガニー・ウィーバー
難病(たぶん白血病)の母と二人で暮らす少年、コナー。
夜には悪夢にうなされ、昼には学校でイジメられる。
家に帰れば母親はずっと病床に臥せっている…。
そんな日々鬱屈を抱えるコナーのもとへ、ある日突然巨大な怪物が現れる。
怪物はコナーに
「これから三つの物語をお前に聞かせよう」
「聞き終わったら最後の四つ目の物語をお前自身が語るのだ」
と謎めいた条件を提示してくるのだった。
過酷な現実とファンタジーの対比
過酷な現実に悩まされる子どもがファンタジー世界に迷い込む――というくだりは『パンズラビリンス』によく似ていますね。
ファンタジー世界で一定数の試練を課せられるところとかも含めて。
しかし試練の目的がはっきりしていていた『パンズラビリンス』と比べ、『怪物はささやく』で怪物が語る物語は「だから何やねん!」と言いたくなるような意味不明な寓話。
実際、コナー自身も「な、何が言いたいんだよ今の話は!?」と困惑してしまします。
しかしこの意味不明さこそコナーの人生に大きく関わる重大な要素であることが、ストーリーが進むに連れ明らかに。
現実と夢想がリンクするこの感じ…これぞファンタジーって感じ!
なお物語の映像は水彩画風のアニメーション。これがまたとっても綺麗で。
「水彩画風」って点が単なる演出に留まらず、物語としても重要なカギになっているのがますますステキ。
怪物の語る物語は何の意味があるのか?
4つ目の物語とは何なのか?
そして怪物は何者なのか?
すべての疑問が収束するラストシーンは涙腺決壊必至です。
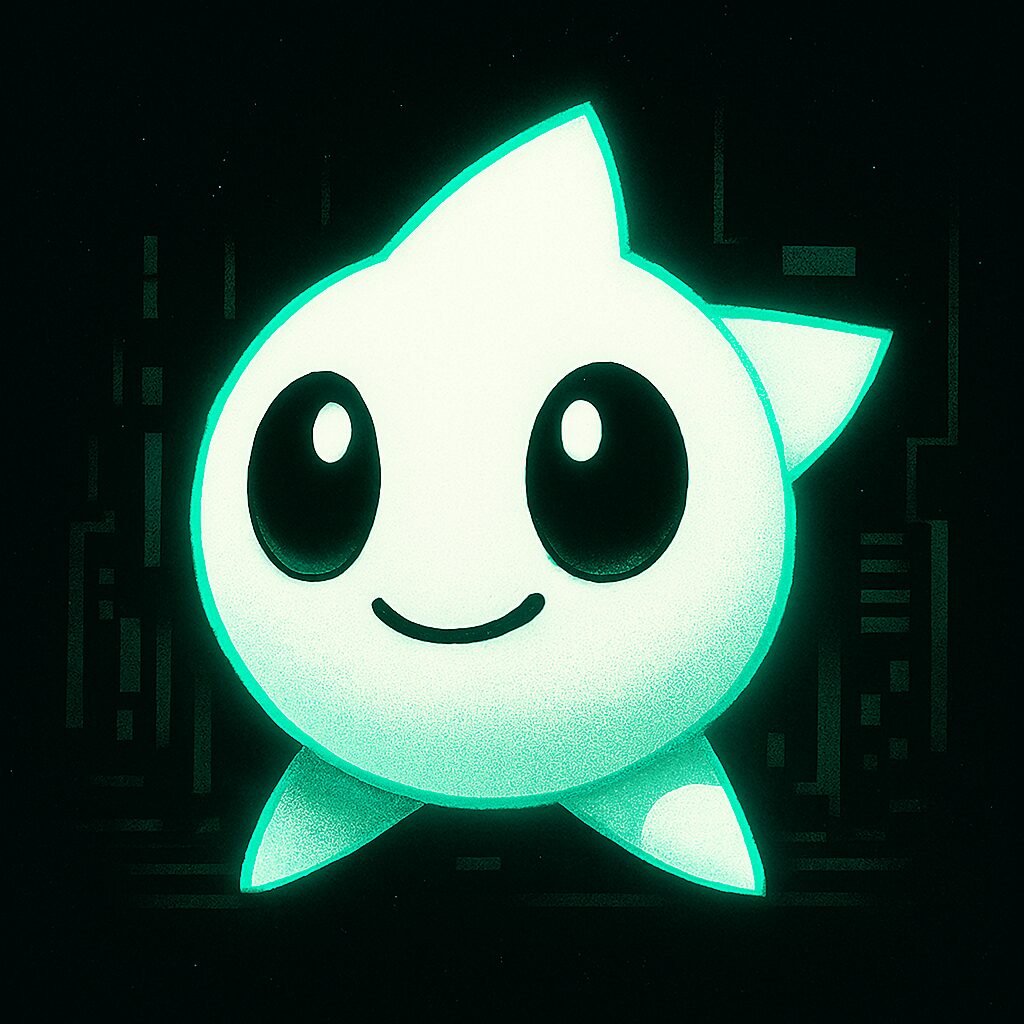
以下の記事 ネタバレ注意です!
明かされる怪物の正体
自分で認めたくない感情に自分で気付く
本作の魅力は終盤の展開の見事さに尽きます。
実は怪物の語る物語は、すべてコナー自身を取り巻く状況の暗喩でした。
まあそれ自体はヤッパリネなのですが、その周辺設定が凄く奥深い。
病床で痩せ細っていく母親とともに暮らすのが余りにも辛く悲しく、こんな思いをするくらいだったらお母さん早く死ねばいいのにと心のどこかで思っていたコナー。
そんな自分に罪悪感を抱くコナーは、自分に対する罰のつもりでわざとイジメられていた訳です。
そしてその孤独感が、周囲への破壊衝動として表出していた…。
怪物との交流の中で、ついに自分の中の真実へとたどり着く少年なのでした。
妄想である怪物の実在性
そして怪物に諭され、母親の死を望んでいた自分さえも受け入れるコナー。
最も素直な気持ちを口にしつつ、愛情深く母親を看取るのでした…。
このシーンがもう珠玉で。
何が凄いって、死の間際に母親が怪物をはっきり「見る」んですよね。
このときの母親の表情が何とも言えず味わい深くて。
ここまで怪物は明らかに幻想として描かれていました。決して現実じゃない。
登場するたび怪物が破壊する家や壁は次のシーンではすっかり元通りだし、そもそも街中で堂々登場してもコナーにしか怪物が見えていない。
観客はもちろん、コナー自身も怪物を「夢」と認識していました。
でもラストシーンで母親の視線が語るのは、決してそうじゃなかったという事実です。
たとえ現実じゃなくても、それは存在しなかったこととは同義ではない。
怪物は確かにコナーに癒しをもたらしたのでした。
怪物自身が母親だったのか、それとも母親が何らかの力を使って怪物を出現させていたのかは分かりません。しかし怪物がコナーのただの妄想ではないことははっきりしています。
この現実と虚構のラインをボカす巧みな演出…映画マジックですね!
シガニー・ウィーバーの悪目立ちがノイズに…
ただ不満と言うか、モッタイナイと思わせる点も多々あり…。
一番のマイナスは、フェリシティ・ジョーンズ演じるコナーの母親がキャラ薄味ってところです。
「この人いったいどういう人なの?」という点がちっとも伝わって来ず、イマイチ最後の感動に結びつかなかったのは本当に残念。
何が悪いって、祖母役のシガニー・ウィーバーが顔面力ありすぎて他を完全に食っちゃってるんですよね。バランス悪いと言わざるを得ない…。脇役に徹するにはマッシヴ過ぎる存在感です。
せっかく『スターウォーズ/ローグワン』とはかけ離れたガリガリ瀕死ボディを披露したのに、活かしきれていないフェリシティ・ジョーンズ…。
モッタイナイ。
あと屁の役にも立たないくせに大人ぶってるパパが心底ムカつきましたが、こっちはこういうキャラってことで納得することにします。離婚、正解。
それから賛否分かれるところだと思われますが、母親の形見のスケッチブックを最後に登場させたのは蛇足だと感じました。
スケッチブックに描かれる「水彩画風の」物語の挿絵や怪物自身の姿…。
怪物の存在は決して幻想ではなかったと示す感動のシーンですが、同じ内容をくだんの「母親の視線」で語ったばっかじゃん!クドいよ!
あくまで個人的にはですが、クドクド説明されるよりも登場人物の一瞬の表情の機微の方が多くの感動を伝えられるんじゃないかな~と思いました。とさ!

感動作を探しているならこっちの記事もおすすめよ。



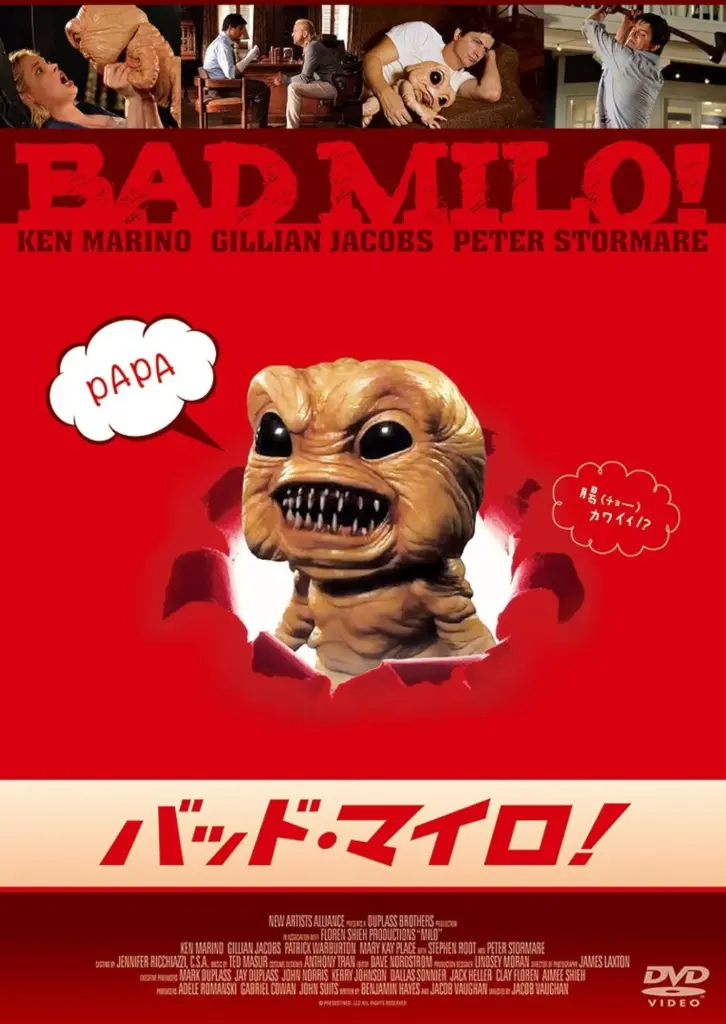

コメント